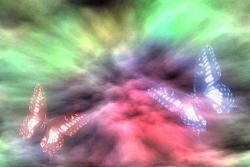第二話 邂逅(2)
その時だった。
廊下をドカドカと歩いてくる大きな足音が鳴り響き、部屋のドアに勢いのよいノックが聞こえた。
「おい!!
アンドレス、いるか?
入るぞ!!」
アンドレスが答える間もなく、はじけるように勢い良くドアが開かれた。
そして、黒い巨大な塊が飛び込んできたかと思うと、それは一人のインカ族の男だった。
隆々たる筋骨の逞しい、がっしりとした、見上げるような大男である。
年の頃は30歳前後だろうか。
褐色の顔に立派な髭をたくわえ、一見いかにも荒々しい印象を与える。
しかしその風貌には、どことなく風格があった。
「おお!!
アンドレス、戻ったか!」
その声も、いちいちでかかった。
ふいをつかれたように、アンドレスはそちらを振り返った。
男は目を見張っているコイユールに、はたと気付き、一瞬、彼も目を丸くしたが、すぐに茶目っ気のあるウィンクを彼女に送ってきた。
「なんだ、アンドレス!
おまえ、いつのまにこんな彼女…」
「そ、そんなんじゃ…ないんです、叔父上!」
アンドレスがすかさず遮ったが、男は冷やかすようにニンマリ笑ってズカズカと部屋に入ってきた。
「まあ、そう隠すな。
みずくさい」
「いえ、本当に、普通の友達なんです」
コイユールが急いで弁明すると、アンドレスもうんうんと必要以上に頷いた。
が、少し耳が赤くなっている。
男はガハハと豪快に笑い、腕を組んで二人をかわるがわるに見渡した。
「わかった、わかった。
まあ、いいさ」
そして、アンドレスの方に近づき、褐色の岩の塊のようなゴツゴツした筋肉質の手を置いた。
「アンドレス、元気そうでよかった!!
今日クスコから戻ると聞いて、来てみたんだ」
男の手の重量感が、アンドレスの肩にずっしりと伝わってくる。
アンドレスも平静を取り戻し、笑顔で大男を見上げた。
「叔父上、お会いしたかった!」
「おお、そうか、そうか!」
男は笑顔でアンドレスの肩を満足気にバンバンと叩き、それから、近くにあった椅子にどっか、と腰掛けた。
椅子が床に沈むのではないかと、内心コイユールはハラハラしながらその様子を見守った。
「クスコの神学校では優秀な成績をおさめているとフェリパに聞いたぞ。
頑張っているな。
実際、いっぱしの若者になってきた」
男は再び満足気に少年を眺めた。
その眼差しには、親が子を見るような、そんなあたたかさと厳しさの両方が宿っていた。
「だが、おまえもそろそろいい年頃だ。
あんなスペインかぶれの学校だけでは、本物のインカの若者には足りない」
「はい、叔父上」
アンドレスも、その意味をよく察して素直に頷いた。
「明日の晩、久々にこの屋敷に皆で集まろうと思う。
お前も顔を出せ」
「是非にも!!」
アンドレスは、間髪入れず、待っていたとばかりに返事をした。
その声には、凛とした力がこもっていた。
大男は笑みを返して、椅子から立ち上がった。
「邪魔したな!
許せ」
それから、コイユールの方にも軽く片手を上げて、ドアを閉めるのにも頓着せず立ち去った。
男が出て行ったのを確認して、アンドレスはドアを閉めた。
「驚かせて、ごめん。
今のは俺の叔父上で、つまり、母上の兄なんだ。
この近くに住んでいて、父上が亡くなってからは父親がわりみたいに俺や母上の面倒を見てくれている」
「そうだったの」
コイユールは納得した。
「それで…明日、何かあるのね」
アンドレスは少し間を置いてから、短く答えた。
「時々、親族が集まっていろいろと話をするのさ」
「親戚の人たちの集まりなの?」
「まあ、そんなもんかな」
と言うアンドレスの横顔はやや紅潮しており、興奮と緊張の色が見えた。
それ以上アンドレスが何も言いそうにないのを確かめてから、コイユールは窓の外に目をやって、すっかり薄暗くなっているのに気がついた。

「いけない、そろそろ帰らないと」
「送っていくよ」
「ううん、いいの。
私なら大丈夫だから」
彼女は首を振って、アンドレスを制した。
しかし、アンドレスはコイユールに付き添って、薄暗くなった帰路を共にした。
「大丈夫なのに…」
コイユールはフェリパ夫人からもらった高級そうな野菜を見下ろした。
「本当は、こんな…、いただくつもりで来たんじゃないのに」
「お金じゃないんだし、それくらいもらってくれたっていいだろう」
「それは…とてもありがたいけど」
普段は、お金ではなくても一切ものを受け取ることはしなかった。
が、フェリパ夫人とアンドレスの前では、つい気持ちが緩んでしまうようだった。
そして、コイユールは、つと立ち止まった。
そろそろ民家もまばらになり、これ以上先まで送ってもらうのは逆に高貴な身なりをしたアンドレスの身の方が案じられる。
「ここまでで大丈夫よ。
どうもありがとう。
それに、本まで…どうもありがとう!」
そう言って、彼女はアンドレスに微笑んだ。
(また会えるのは、いつになるかしら…)
微かに胸の奥が痛む。
コイユールは、アンドレスからもらった本を握り締めた。
やはりアンドレスと長期間離れるのは寂しいことだった。
でも、仕方のないことである。
暫く物思いに耽ったように黙っていたアンドレスが、ふいに口を開いた。
「コイユール、明日の今頃、またうちに来てみないか」
「え?」
突然のことに、コイユールは目を見開いた。
「君は、さっき言ったよね。
もし皇帝陛下が生きていたら、この国を俺たちインカの手に取り戻せるのか、って」
アンドレスの表情はこれまで見たこともないほど、真剣だった。
「コイユール、君は何を考えてる?
なぜ、あんなことを聞いたんだ?」
アンドレスの眼差しの鋭さに、一瞬、コイユールは、自分が睨みつけられているのではないかと思ったほどだった。
彼女は、微かに身を縮めた。
しかし、視線をそらすことはしなかった。
アンドレスの瞳を見つめ返すコイユールの瞳は、清く、澄んでいた。
自分の心の奥底で、何かがはじけたような強い感覚を彼女は覚えた。
二人は暫し無言で見つめ合った。
「私、このままでいいとは思わない…!」
言葉を発したのは、コイユールの方だった。
彼女の瞳が、強い意志を秘めて、揺れていた。
それ以上は言葉にならなかったが、アンドレスはその瞳に強く頷き返した。
「そうだ。
このままでいいはずがない!」
アンドレスの瞳の奥に、激しく燃え上がる炎を見た思いがした。

一つ一つの言葉をかみ締めるように、アンドレスは再び言った。
「明日、待っているよ。
もし、君が、本気でこの国を変えたいと思うなら、きっと意味があると思う」
そう言い残して、アンドレスは踵を返した。
その後ろ姿が夜の闇に消えても、コイユールはしばし動くことができなかった。
彼女は自らの心の奥底を、ふいに覗いてしまった気がした。
それは、どこかで蓋をして見ないようにしていたかもしれない、自分の心の叫びだった。
そうだ…!!
私、この国のこと、このままでいいなんて思っていない…――!!